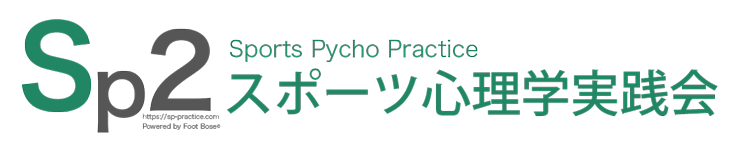どうも河津です。普段僕はスポーツ選手を相手にすることが多いのですが、最近はありがたいことに日本代表クラスの方にサポートすることもしばしばあります。
その中で感じるのは、ストレスの原因が一般の方よりもとても多くなっているということです。
結果へのプレッシャーは言うまでもないことだと思いますが、ほかにも現代社会におけるコンプライアンス問題(少しやりすぎなんじゃないかなと個人的には思うところもあります)によって日常生活・言動をかなり極端に制限されること、スポンサーや応援してくれる人たちへの責任感、ドーピングへの細心の注意、限界まで肉体に負担をかけるハードワークなど、挙げればきりがありません。
そんな中を生き抜いていくのだからよほど心が強いのでしょうね!なんて思う方は多いと思いますが、普段彼らに接している立場から言わせてもらうなら、全くそんなことはありません。
一流のスポーツ選手=もともと一流の健全な心を持っている では決してないのです。
もちろん例外もありますが、ほとんどの選手は後天的にトレーニングによって健全な心を手に入れています。残念ながら手に入れられなかった選手は人知れず競争から脱落することもしばしばみられます。
それでは、一体どのようなトレーニングをしているのか?ということが皆さんの気になるところだと思いますが、今回はいろいろあるトレーニング方法の中で現在僕が最強だと思える方法を紹介します。
YouTubeでも効果的な瞑想のやり方を紹介しておりますので、こちらも見てみてください。↓ 記事の後半では、科学的な解説も行いますので興味のある方は是非ご覧ください。
記事の後半では、科学的な解説も行いますので興味のある方は是非ご覧ください。
ストレスに強い心を作る最強のトレーニング法「瞑想」
瞑想というと皆さんがイメージするのは座禅でしょうか?そのイメージでほぼ間違いありません、仏教における禅≒座禅はまさに瞑想の方法論の一つとして考えられます。以下に、そのやり方を紹介します。このやり方は、実際に僕が通っている禅寺の教える作法になります。
大きく分けて手順は3つ
- 姿勢を整える
- 呼吸を整える
- 心を整える
です。この順番で心を整えていきます。以下で詳細に解説していきます。
①姿勢を整える
座り方を決める
まずはあぐらをかきます。本来は胡坐をかいてやりますが、あぐらが欠けないようであれば椅子に座っておこなっても大丈夫です。
あぐらをかく場合は左の画像のように足を組みます。結構きつい組み方になりますので、足が痛くなるなら右の画像のように片足だけで大丈夫です。


また、下の画像のように、座布団は2つ使っておしりを高くすると楽に座禅ができますのでお勧めです。

椅子で行う場合は,深く腰掛け過ぎず、背筋はまっすぐ、骨盤が立つように座りましょう。座り方が決まったら以下の手順で上半身の姿勢を整えていきます。
背筋を整える(あぐら・イス共通です)
座った状態で体を左右に揺らしながらちょうど重心が真ん中になるように止まります。次に体を前後に揺らして、またちょうど重心が真ん中になるように止まります。顔はまっすぐ前を向きます。
手を組む
手はおへその前で組みます。組み方は左手の親指を右手で握って、左手で右手を覆うような感じ(左右逆でも構いません)で軽く包みます。手を組むのが難しい人はリラックスしておへその前に置くだけで大丈夫です。
視線
顔はまっすぐのまま1m先の床に視線を落とします。そうすると半眼になります。目はつぶっても良いですが、正しい作法は半眼です。
②呼吸を整える
呼吸はゆっくり楽なペースで腹式呼吸をします(鼻から吸って口から吐く)。
③心を整える
座禅中は自分の呼吸を数えましょう(数息観)。息を吸って吐くときにできるだけゆっくり吐きながら心の中で「ひとーーーつ」吐ききったらもう一度吸って、またゆっくり吐きながら心の中で「ふたーーーつ」。これを「とーーーお(10)」まで繰り返します。10まで行ったらまた1に戻って10まで数えます。
時間は短くても10~20分はしたいですね。ひたすら数息観を続けましょう。
ここで紹介した数息観以外でも、自分の吐く息が唇を通っている感覚だけにひたすら注意を向けるなど、マインドフルネスの技法を取り入れることも有効です。
まずは、座禅を組みながら、身体の感覚や呼吸などの特定の対象のみに意識を向け、それを維持し続けるようにやってみましょう。とにかくやってみることが大切です。
セルフモニタリングをプラスする
上記のような瞑想の方法にプラスしてぜひやっておいてほしいのがセルフモニタリングです。合わせてやると効果が上乗せされます。
- 瞑想前の気分・感情・身体感覚
今日あったこと、それに対する気分感情、身体感覚も簡単に書いてみる。この後練習があるのなら、練習に対する気持ちを簡単に書いてみる。
- 瞑想後の気分・感情・身体感覚
終わった直後の気分感情、身体感覚を簡単に書いてみる。この後練習があるなら、練習に対する気持ちを簡単に書いてみる。
セルフモニタリングを取り入れる意義は、自分の感情や身体感覚の変化に対する気づきが高まることによって、瞑想の効果に対する気づきが高まり瞑想自体の効果が上がること。そして、自分の感情に気づきやすくなるので、普段から感情のコントロール能力が高まることです。
瞑想の効果を科学的に解説
ここからは瞑想の効果について最新の研究で分かっていることをわかりやすく解説していきます。現代の脳・神経科学の分野ではfMRIという脳の活動を画像で分析できる方法などが発達してきており、瞑想している時、脳内でどのようなことが起こっているかが明らかになってきています。
デフォルトモードネットワーク
近年の脳の研究で多く報告されてきたのがこのデフォルトモードネットワーク(以下DMN)という脳領域のネットワークでした(場所で言うと内側前頭前野、前部帯状回、後部帯状回など)。このネットワークが活性化するのは、人が何も作業をしておらず安静にしている時で、いわゆるぼーっとしている時です。
DMNは実は非常にエネルギーを使うんですね、だからただぼーっとしてても実は脳は休まっていません。そして、このぼーっとしている時に人っていろいろ考えてしまうのです。この状態をマインドワンダリング(以下MW)と呼びます。
MW自体はさほど悪いわけではありません。問題はこの状態が過剰になってしまうこと。MWが過剰になってしまうと不安や抑うつにつながってしまうと考えられており、頭も疲れるし、不安が大きくなってしまいます。
大事なのはDMNやMWを適度にコントロールすることなのです。

瞑想がDMNやMWに与える影響
そこで注目されたのが今回ご紹介した瞑想なんですね。実際多くの研究で、瞑想がDMNの活動やMWを低下させるという報告があります。
呼吸に意識を向けたり、呼吸の数を数えたりして意識をという特定の対象に集中させると、DMNの関連領域や、情動反応の主要な部位である偏桃体の活動を抑制するという反応が脳内に起こります。その結果、DMNの活動が低下し、MWも抑えることができるのです。
そのことが、心理的には不安や抑うつの低下、集中力の向上。身体的には自律神経の安定、睡眠の質の向上など様々な良い効果につながっていくのです。
安静時と瞑想時の脳波の違い
また安静時と瞑想時では発生する脳波にも違いがあることが明らかになっています。安静時にはよく聞くα波という脳波の波形になることが分かっていますが、瞑想中にはθ波やγ波などの高度な集中状態を表す波形がでてきます。
瞑想状態は明らかに安静時とは違った脳の状態なのです。

<参考文献>
- 苧阪 満里子(2013)デフォルトモードネットワーク(DMN)から脳を見る。生理心理学と精神生理学、31(1)、pp.1-3。
- Gotink, R. A., Meijboom, R., Vernooij, M. W., Smits, M., & Hunink, M. M. (2016)。8-week mindfulness based stress reduction induces brain changes similar to traditional long-term meditation practice–a systematic review。 Brain and Cognition、108、32-41。
- Masahiro Fujino, Yoshiyuki Ueda, Hiroaki Mizuhara, Jun Saiki, & Michio Nomura (2018) Open monitoring meditation reduces the involvement of brain regions related to memory function
Scientific Reports。